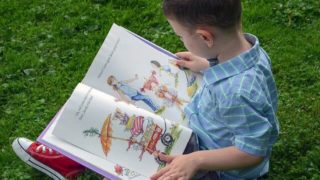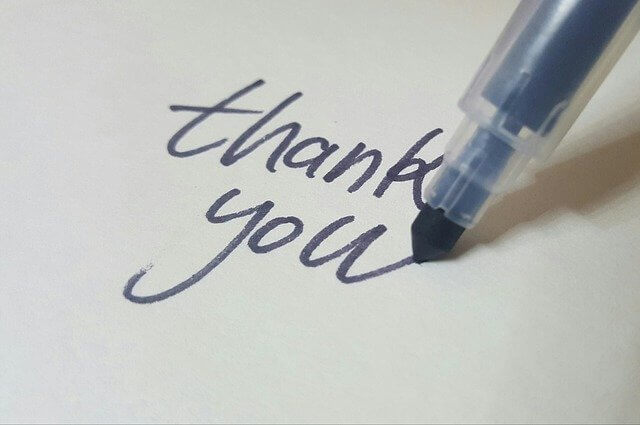卒園の時期がやってきました。
この時期になると、ママさんによっては卒園に関する準備で忙しくなりますよね。
役員経験があると謝辞をお願いされたりして、「あ~、なんて書いたらいいんだぁ~」と頭を悩ませたり、「泣いちゃったら嫌だな~」と不安になったりと、落ち着かないなんて方もいるかと思います。
そこで今回は、卒園式での謝辞の「基本的な書き方」「ポイントや例文」「文字数や長さ」などを、また、読むときの「緊張や泣くのを防ぐ方法」についてもご紹介します。
卒園式の謝辞 オリジナルを作るための基本
まずは、謝辞の意味を確認しましょう。
謝辞とは「お礼を述べること」で、お祝いの言葉(祝辞)とは異なります。そのため、園児や保護者への「おめでとう」という言葉はいりません。
つまり、保育園や幼稚園における謝辞とは何かというと、園児の親である私たちから、園でお世話になった先生や関係者の方々へ送る感謝の言葉なのです。謝辞をつくる時にはまず、この点をおさえておきましょう!
卒園式の謝辞は何分くらい?何文字程度?
卒園式の謝辞では、3分~5分程度の長さが理想です。文字数でいうと、800文字から1000文字程度ですね。
20字×20字の原稿用紙なら1枚400字なので、1000字なら原稿用紙で2.5枚になります。
次は、それを踏まえて謝辞の流れ(構成)を確認していきましょう。
謝辞 卒園式での基本構成
基本的な構成は8項目あります。
1.季節の言葉(時候の挨拶)
まずは、季節を感じさせるひと言を入れます。
「時候の挨拶」と検索すればたくさん出てきますので、3月中旬から下旬にふさわしいものを選ぶようにします。
また、卒園式当日は晴れとは限らないので、「雨でも晴れでも使えるような言葉」を選ぶか、「2パターン用意」しておくと安心です。
2. 園や来賓へのお礼
次に、卒園式を開いてくださった先生や関係者の方々、そして、式に参列してくださったご来賓の方々へのお礼を述べます。
3.保護者代表のあいさつ
ここで、保護者を代表して挨拶することを述べます。
・僭越ではございますが、保護者を代表いたしましてご挨拶申し上げます。
など、可能であれば「僭越」という言葉を入れます。
4.思い出・エピソード
ここは、一番悩ましい所であり、泣く、泣かせるポイントでもあります。
入園してから3年間程度の行事を振り返り、具体的なエピソードを盛り込んでいくのですが、ポイントは行事を2~3こ選ぶこと。季節が偏らないようにすることも大切です。
5.成長の喜び
「4」に続きここでは、
など、成長した子どもの姿を喜ぶ一文を入れます。
すると、
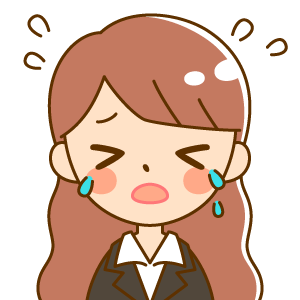
成長したよぉ~。
となるので、ここが一番、思わず泣くポイントになるかもしれません。
6.園や先生方への感謝・お礼
子どもたちが成長できたのは、先生や職員の方々のおかげであることを伝えます。
など、「それもひとえに・・・」とつなげるとスムーズです。
7.子供たちの今後
小学校へ入学する子供たち不安や期待を入れます。
ここはあえて入れないか、「5」の後半に入れるのもありです。
8.締めの挨拶
園の今後の発展や、先生方、職員、関係者の皆様のご健勝をお祈りします。
9.日付と氏名
最後は、日付と代表者の名前を入れます。こんな感じです。
保育園や幼稚園での卒園式 謝辞の書き方と例文
1.季節の言葉(時候の挨拶)
2.園や来賓へのお礼
本日は、このような心温まる卒園式を開催していただき、お忙しい合間を縫ってご準備いただいた先生方に厚く御礼申し上げます。
また、ご来賓の皆様におかれましても、日頃より、子供たちを温かなまなざしで見守っていただき、誠にありがとうございます。
3.保護者代表のあいさつ
4.思い出・エピソード
思いおこせば、初めて園の門をくぐった入園式のあの日、緊張していた私たち親子を先生たちの優しい笑顔が迎えてくれました。気持ちがふっと和らいだのを今でも鮮明に覚えています。
入園してから本日まで、園では様々な行事がありました。
入園してすぐに行われた参観日。親元を離れたばかりで心配する私たちの不安をよそに、楽しく元気に遊ぶ子供たちの笑顔を見て、ほっと安心することができました。
秋に行われた運動会。かわいらしい演技から、元気いっぱいに走るリレーまで、親子みんなで熱くなりました。
そして、冬の生活発表会。緊張した表情を見せつつも、一生懸命大きな声で歌や演技を披露してくれました。
5.成長の喜び
時にはわがままを言ったり、反抗してしまったりする子供たち。この日ばかりは、普段はなかなか見られない大人のような雰囲気を醸し出していました。
私たち親は、一人一人のその姿に感動し、涙をこらえるのに必死でした。親の気が付かない間に、子供は成長していることを実感した瞬間でもあります。
6.園や先生方への感謝・お礼
どの行事も、子供たちだけの力では成し遂げられませんでした。ひとえに、園の皆様の温かく、そして時には厳しいご指導の賜物だと感じております。
普段より、生活の様々な場面で子供たちを見守り続けてくださった先生方、美味しい給食や、きめ細やかな心配りをして下さいました職員の皆様、心より感謝申し上げます。
7.子供たちの今後(ここは省略するか「5」の後半へ入れるパターンもあり)
本日こうして、静かに座り卒園式に臨んでいる子供たち。皆様に見守られて、身も心も、一回り、二回りと大きくなりました。
笑い声や元気な歌声が響き渡った思い出がたくさん詰まったこちらの園舎とも、もうお別れです。
今は、優しい先生方や仲良しの友達と離れ離れになり、親子ともども不安いっぱいの時期です。
春は別れの季節でもありますが、新しい出会いの季節でもあります。新しいお友達とともに、楽しい小学校生活を送ってくれることを切に願っております。
8.締めの挨拶
9.日付と氏名
卒園式の謝辞 読み方のポイントは?
謝辞を読む際、感極まって泣いてしまうことがあるかと思いますが、聞き取れないほど泣いてしまうのには少々問題があるかと思います。
かといって、淡々と読み進めてしまうのもあっさりしすぎてしまいます。
涙をこらえつつも、参列している方々に思いが伝わるように、落ち着いて、そして、心を込めて謝辞を述べる事が大切だと思います。
また、原稿をじっと読むのではなく時折顔を上げて、皆様の反応を見ながら話されることも重要です。
卒園式での謝辞エピソード 緊張や涙を防ぐには?
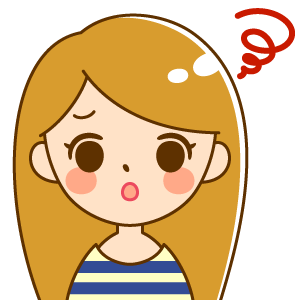
卒園式の謝辞の準備はできたけど、ちゃんと読めるか心配だなぁ。
謝辞を読むのって、緊張してしまいますよね。もし、緊張しすぎて言葉が詰まりそうになったら「泣くのを我慢しているフリをする」なんて方法もあります。
「完璧に読もう」とか「言葉に詰まってはいけない」とか考えすぎてしまうと、ますます緊張してしまうかもしれないので、緊張してつまずきそうになったら「上を見上げて」みましょう。「泣くのを我慢しているのかな?」と、思われるくらいで何にも問題ありません。
またこれは、本当に泣きそうになって困った時にも使えますよ!実際、泣きそうになって何度も上を見上げて涙をこらえたというママも、涙をこらえて読み切ったら「よく頑張ったね」と、役員仲間から労いの言葉をかけられたそうです。
じゃあ、泣いたらダメなのかというと、そんなこともありません。号泣しすぎるのは避けたいところですが、こんな経験をしたママも。
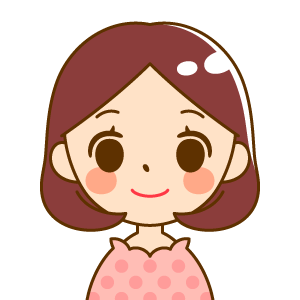
思わず泣いてしまい1分間、会場をシーンとさせてしまいました。
この沈黙は先生や保護者に涙を誘い、会場全体が涙となったそうです。しかし、泣いたことは非難されることはなく「謝辞、良かったよ」と絶賛されたんだとか。
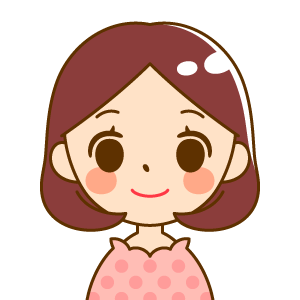
泣きたくない人は、視線の先に注意ですよ!
号泣するのを防ぎたい人は、先生や子供たちを見ないようにするといいそうです。
まとめ
「泣く人もいれば、泣かない人もいる」また、「スラスラと読める人もいれば、言葉を詰まらせながら読む人もいる」謝辞ですが、大事なのは「感謝」の気持ちを園や先生たちに伝えることです。
「ありがとうございました」という、一言だけを伝えるんだと思えば、緊張は和らげることができるかもしれません。
▼おすすめ記事
>>幼稚園での謝恩会トラブル2選!体験談から学びたいトラブル回避方法
>>保育園の謝恩会トラブル|体験談から学びたいトラブル回避法
>>子育て向いてない、やめたい|母親でいることに疲れたら試したい5つの事。